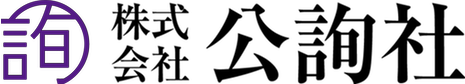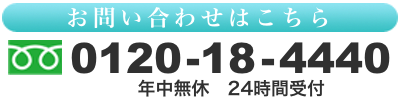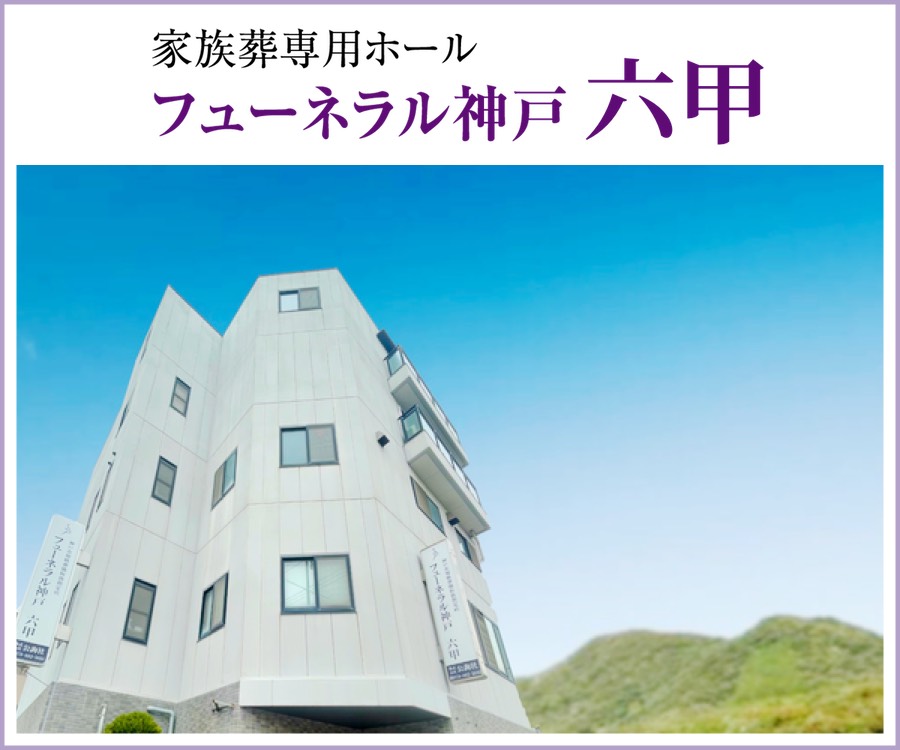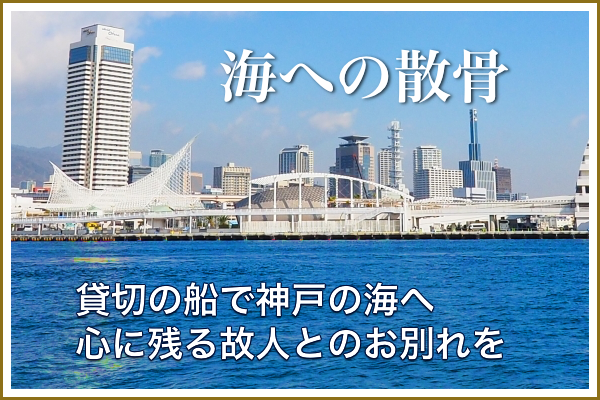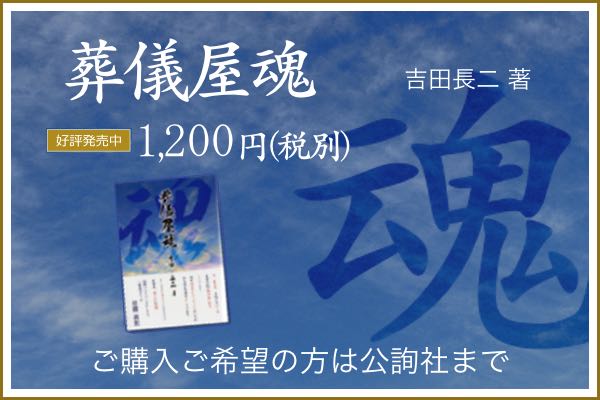公詢社ブログ 葬儀屋のつぶやき
葬儀のポイント
2018.12.15
ロウソク
仏前の明かりは本来、灯心に種油を使って灯すものですが、現在では大部分が
ロウソクであり、さらに一部では電灯も使われます。
ロウソクには、仏様に灯りを供えその余光で自分自身の道をも照らしていくという
意味合いがあります。
【由来】
人が火を使用した起源は極めて古く、中石器時代から紀元前7000年~8000年頃と
推測されます。この当時、火を使用する目的は夜間猛獣から身を守る事にあり、
次第に照明、暖、食物の加工にと利用されていきました。
後に夜の警護や照明の為に焚く火をかがり火と呼ばれますが、その後一本の
つけ火による灯火が発明され、樹脂の多い松の木を束ねたものが考案されました。
2018.11.19
祭壇
人の死。これは避けて通ることの出来ない事柄であり、
その御霊を見送りのが人々の務めです。
その一つの方法として祭壇が自然に生まれてきました。
古き時代よりどのような形にせよ、葬儀のための飾り壇らしきものは
あったと思われます。
現在の形に至るまでかなり様変わりしていますが、その飾り役の主役は
今日に至るまで、位牌・灯り・盛物の三役であることは紛れもありません。
この内、位牌は中心的なものであり、材質もおもに白木材で作られています。
位牌の『位』は、敬意を表す言葉であり、『牌』というのは、木札ということです。
灯りの原点は、死者の枕元に置く行燈が最初に使われた通称『枕あんどん』と言います。
これは、死者が浄土に旅立つ為の灯りという意味を持っています。
その他、雪洞(ぼんぼり)・灯篭(とうろう)・六灯(ろくとう)などの形が作られ、
灯りをつけて飾られました。
六灯は仏教の六道輪廻(ろくどうりんね:六道の間を生まれ変わり、死に変わりして
迷いの生を続けること)の教えが表されています。
六道とは、衆生が善悪の習わしによって、おもむき住む6つの迷界です。
【地獄(じごく)】
現世に悪行をなした者が、その報いとして死後に苦果を受ける所。
【餓鬼(がき)】
三悪道・六道・十界の一つ。
ここに住む者は内障・外障によって飲食することが出来ず、常に飢餓に苦しむ。
【畜生(ちくしょう)】
生前に悪行をなした者がおもむく世界。
地獄より上だが禽獣(きんじゅう:鳥や獣)の姿に生まれて苦しむ。
【修羅(しゅら)】
阿修羅の住む争いの絶えない世界。
【人間(にんげん)】
人間の住む世界。
【天(てん)】
人間世界より優れているが、いまだ輪廻を逃れられない。
2018.09.10
お葬式とは
近年インターネットで葬儀会社を紹介する企業が増えてきております
本来お葬式とはご遺族・宗教者・葬儀社との話し合いによって決まっていくものです
公詢社はお客様と直接対面して葬儀の費用や形式など細かな事までご相談させて頂きます
大切な人の人生最後の儀式
私たちはご遺族と共に考えます